支援先写真集09-10.pdf へのリンク
|
2017年5月-2018年6月期、WFFは、アジアやアフリカで自立支援の活動を行う7つの団体の
プロジェクトを支援しました。
→ 支援先写真はこちらから 写真はこちらから
|
2016年5月-2017年6月期、WFFは、アジアやアフリカで自立支援の活動を行う7つの団体の
プロジェクトを支援しました。
→ 支援先写真はこちらから 写真はこちらから
|
2015.年5月-2016年.6月期、WFFは、アジアやアフリカで自立支援の活動を行う7つの団体の
プロジェクトを支援しました。
→ 支援先写真はこちらから
|
| |
〜EDFのシマンバさんに会いに行きました
|
 |
WFFでは久しぶりのスタディツアーとして栃木県那須塩原市の学校法人アジア学院(アジア農村指導者養成専門学校)へ、2005年12月3日土曜日、東京駅に9名が集合して訪問してきました。別の目的としてはアフリカ・ザンビアのEDF(エキュメニカル開発基金)のシマンバさんに会うことでした。WFFでは1999年から毎年約10万円をEDFへ支援してきました。その支援金の報告とグループの現状を聞くことが、広大なアジア学院の農場見学の後にできました。 |
| <アジア学院の遠藤さん、シマンバさんと参加者の皆さん> |
|
 アジア学院 アジア学院 |
|
|
 |
アジア学院は1973年の創立以来アジア・アフリカの農村地域から、その土地でその土地の人々と共に働く農村指導者を学生として招き、実践的な学びを行っているユニークな学校です。9カ月間(4〜12月)の研修は、命を支える「たべもの」作りにこだわり、有機農業による自給自足の生活を基盤として、自国のコミュニティーの自立を導く人材を養成しています。海外からの学生の渡航費・研修費をほぼ全額負担し、アジア学院ではその活動を寄付でまかなっています。
駅までマイクロバス(相当使い込まれた!)にお迎えに来ていただき、首都圏事務所長の遠藤抱一氏の案内で、樹木に囲まれた丘陵地の広大な農場を約1時間半見てまわりました。敷地の1/3が森、1/3が畑 残りの1/3がいろいろな建物で占めれているそうです。 |
|
有機・循環農業のモデル |
 |
まず倉庫から見学です。混合飼料を、購入するのでなく自前の家畜の糞や大豆カスなどを配合して飼料から作るので、それらの材料や、収穫した米などが山積みされていました。向かいの農機具の小屋には、子供の頃見たことのある懐かしい鋤や鍬がたくさん並んでいました。発展途上国では、現在の日本の機械化した農法でなく、これらの道具が大活躍なのです。アジア学院では豚などの糞を溜めてメタンガスを作りエネルギーとして使うこともしています。途上国では木を切りマキを作ることにより自然が破壊され、砂漠化の原因にもなっています。無駄をなくし組み合わせを考えて、お金が無くても成り立つ循環型農業のモデルを研修生に見せて学んでもらうのです。
|
| <池> |
 |
豚の飼育方法も色々あるようで、韓国式の糞も尿も回収せず、おがくず(?)と混ぜ合わせた見たところフワフワでとても心地よさそうな豚舎もあれば、子豚が古コタツにぎゅうぎゅうに固まっていたりもしました。
|
| <子豚たち(韓国式飼育法)> |
|
 |
池では安く良質な蛋白質となる鯉を飼い、すぐ近くでは大切な水を確保するための「上総掘り」の井戸がモデルとして掘られていました。
少し上ったところの畑では50〜60種類の野菜が栽培されるそうです。12月なのでほとんどの収穫は終わっていて、見られず残念でした。
鶏小屋のなかにはウサギが共に飼われており、なんとも不思議な光景なのですが、ウサギの尿が鳥のダニを殺すので、薬剤を使わずにダニの発生を押えられるそうです。 その他には三種類の牛、ヤギに会いました。
|
| <収穫のおわった畑> |
|
 |
宿舎の近くの炭焼きの釜の前では、韓国の方が黙々と木を割っていました。炭は水の浄化や動物の整腸作用やえさ・肥料に、また木酢液は虫除けになるそうで大変有用です。また山の斜面を利用したしいたけ栽培のところへも行きました。
ここでは子どもを増やして売ったり、卵、乳、肉を自分たちで食べ、余剰分はチーズやバター、ハム、ジャム・ピューレなどに加工し、保存する技術も教えています。一番最新の建物が、遠藤氏の立案設計になるそれらの実習作業棟でした。
化学肥料や農薬,機械を使わず、原始的とも言えるここでの農法が、途上国では必須であり、また現在の日本にも、環境保全や命の大切さを知るために必要と学びました。 |
| <炭焼き> |
|
 |
昼食は卒業を間近に控えた研修生と共に、カレー風味の大豆と 肉の炒め物とカボチャのポタージュスープをおいしくいただきました。 |
| <食堂で研修生と昼食> |
|
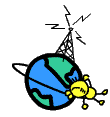 ザンビアのEDF ザンビアのEDF |
 |
午後はシマンバさんからEDFのことを聞きました。カナカンタパ村は飢餓と干ばつとエイズが深刻で、シマンバさんは食品加工を通して農民の収入を少しでも上げる手助けがしたくアジア学院へ来ていました。EDFのリーダー夫妻は共にアジア学院の卒業生で、過去8年間女性と孤児の面倒をみてきました。話し合った結果、生きていくための技術を何か身に付けるトレーニングセンターの設立が一番必要となり、その活動を続けています。開発目標として・食料生産(有機農法)・食品加工・大工仕事・洋裁などの技術訓練・エイズの人々の情報交換の場と支援サービス・少額ローン貸付・収入の増やせる野菜や農作物の種類の特定などがあります。今までWFFでは、養蜂、ジャム作り、鳥小屋、ソーセージ加工機械購入のプロジェクトを支援してきました。また昨年度は生産した農作物を売る店の屋根用資材の購入資金の一部を支援しています。次年度へのWFFへの支援要請プロジェクトは、ひまわりの種の購入資金支援です。ひまわりを育て油を採るために、200世帯を対象に400kgの種を必要としているとのことでした。
シマンバさんは学院での卒業プレゼンテーションをして、翌週には帰国の途につくとのことでした。動物と自然に接して、 多くを学び、 考え、 そしてとにかく楽しい充実した一日でした。 |
スタディーツアー参加者の感想をご紹介します。
| ◆ |
「無駄なく全部をまわして使うことを学ぶ、そのことが大切なのでなく、アジア学院では学びに 来ている研修生が、そのようにできることを知る ことが大切」 |
| ◆ |
「途上国の研修生が学ぶだけでなく、現在のわれわれ日本人が学ぶべきこと」 |
| ◆ |
「日本の子供たちにも、命をいただいて生きていることを実際に目から学ぶワークキャンプのあることに感銘した」 |
| ◆ |
「私達はすぐにお金を出して買うが、人が生きて食べていくことは、大変なんだなー」 |
| ◆ |
「ここで学んでいる人たちは、自分のためでなく、人のためにしていることを考えさせられた」 |
|
| ● PSHFのプロジェクト スタディーツアーの報告書 |
|
|
PSHFのプロジェクト スタディーツアーの報告書が完成しましたのでご一読ください。 フィリッピンの恵まれない方々の実体が少しでも理解していただけたらと願っています。 → 報告書はこちらから
|
| ● PSHFのプロジェクト スタディーツアーを実施 |
|
|
 |
2001年4月9日から15日までボランティア活動の一環で恵まれない人々への自立支援プロジェクト視察のため フィリピンを訪問した。今回の訪問は支援先NGOでリチャード フォスター氏が主宰するPSHF (Philippines Self Help Foundation)を訪ね、
そこから各個人またはグループへ自立の為の支援している先を訪問し、その実状を視察するためのもので
日本から支援者5名が参加した。
ネグロス島、ボホール島、セブ島、マクタン島、オランゴ島の島々をPSHFのメンバーと共に最終支援先の人々
約20件のプロジェクトを視察するハードスケジュールであった。マニラやゼブ等は良く開けた街であるが、貧富の差が激しく、
またそこから離れた島々にはとても貧しく生活している人々が沢山居ることが分かった。
これらの状況を広く皆さんに知ってもらい、みんなで少しでも恵まれない人々への自立支援ができればと新たな
思いになった。
(写真右はボホール島で木の繊維を織りマットを作り生計を立てる村人と視察者。左端がPSHF現地スタッフのNeliaさん。) |
| ● 2001年 WFF/ILCA協賛お花見チャリティーバザー |
|
 |
2001年4月7日(土)、2001年度お花見チャリティーバザーが千代田区一番町のWFF本部ガレージで開催された。今年はサクラの開花が 早く、満開をかなり過ぎた時期での開催となったため人の入りが懸念されたが、晴天無風の好天気に恵まれ、遅い千鳥が淵の花見に 音すれた人が多く参加して頂いたこと、好意にしていただいている隣接の英国大使館のお花見も同じ日となり、大使館でのお花見を終わり 我々のチャリティーバザーに多くの方が駆けつけて頂いたことで売り上げもほぼ例年水準となり、参加した支援ボランティアの人たちをほっとさせた。
|
 今回のチャリティバザーの収益はCARA(西アフリカ農村自立協力会の
「マラリア予防薬配布」のプロジェクト)を支援します。CARAはサハラ砂漠に接するマリ共和国
において1990 年から、日本人の歯科医師 村上一枝さんにより始められた団体です。活動は
識字教育・植林・野菜・果樹栽培・改良かまど・保健活動・井戸掘等多面的に行われてい
ます。WFFでは、'94 年から毎年支援をして、トイレづくり・改良かまど・穀物粉砕機、乳幼
児用体重計購入資金等支援してきました。 今回のチャリティバザーの収益はCARA(西アフリカ農村自立協力会の
「マラリア予防薬配布」のプロジェクト)を支援します。CARAはサハラ砂漠に接するマリ共和国
において1990 年から、日本人の歯科医師 村上一枝さんにより始められた団体です。活動は
識字教育・植林・野菜・果樹栽培・改良かまど・保健活動・井戸掘等多面的に行われてい
ます。WFFでは、'94 年から毎年支援をして、トイレづくり・改良かまど・穀物粉砕機、乳幼
児用体重計購入資金等支援してきました。
今回は、現地の村人へのインタビューで好評の「マラリア予防薬の配布」(57ヶ村 3ー4 万人予定)のプロジェクトへの支援要請に応えます。
|
| |
|
|
2001年2月27日(火曜日)午後6時30分より、日本基督教団 霊南坂教会の礼拝堂でチェンバロ奏者の小野真理さんとWFFが協賛し
WFF創立10周年記念チャリティーコンサーを開催しました。
小野真理さんは、文化庁派遣芸術家在外研修員として渡英され、この度帰国されたのを機にリサイタルを開くことになったものです。
演奏された曲目はバッハの「トッカータホ短調」「パルティータ ホ短調」など。
このコンサートの収益金は、小野真理さんのご希望も入れ、パプアニューギニアの農業発展プロジェクトにしました。
支援団体名はLDS(ルーテル開発サービス)といい、
地域開発や小規模ローンなど様々なプロジェクトを展開しています。
今回の「モデル農園」プロジェクトは、二つの大きな目的があります。
一つは放牧状態にある豚を囲って飼育することにより、農作物への被害を減らし作物の収穫量を上げることです。
もう一つは、現地の豚は野生で繁殖率が低いので西洋の豚(おとなしくて多産)との交配で、数を増やしタンパク源をより多く得られるようにする目的です。
このプロジェクトの申請者のMr.Smiziはアジア学院の卒業生でクラスメートにも地域の人たちにも人望が厚く、
エネルギッシュな活動を展開しています。
当日はILCAもバザーを開き新しく入荷した製品もたくさん販売されました。
|
|
|
2000年10月6日、「CanDo(Community Action Development Organization)アフリカ地域開発市民の会」(日本)事務局長の国枝氏、現地コーディネーターの島木氏が来訪。Candoはケニアにおいて、教
育支援、環境保全、保険医療活動の開発協力活動を行う 日本のNGO。ケニア ナイロビのムクル・スラム地域の高校生の補習授業のプロジェクトへの支援要請がある。
ケニアの教育制度は、8(小学校)・4(高校)・4(大学)制だが、就学率は、小学校の85%に対し、高校は24%と低い。
その理由は、授業料が非常に高いこと。しかも高校卒業時に全国で実施される
KCSE(ケニア国家統一中等教育試験)のカリキュラムは莫大なため、補習教育がどうしても必要だが、その費用は一般父兄にもかなり負担な状況の中で、特にスラムの家庭では、とても負担しきれ
ない。
一方、失業率5割のケニアでは、教育のあるなしが就職のかぎであり、スラムの子供は、その面 でも悪循環の状況。そこで、教育面の支援を通して、最終的には良い仕事/収入への途も手助けし
ようとする。
補習授業では、生徒達に勉学に取り組む機会を提供し、授業科目への理解を深め、さらには勉強だ
けでなく広く生徒達の生活している社会に対する興味・関心を高めることを目的とする。12月、4月、8月の高校休業中に約40人(2教室)規模で少額の参加費で行う。総事業費210,240円、支援要請額
120,240円。
今までに支援したことがない補習授業への支援のため、賛否両論だったが、必ずレポートを提出してもらうことで要請額の全額を支援することに決定した。
|